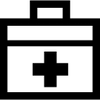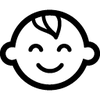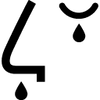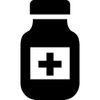突然の頭痛に襲われると、「これは危険な病気のサインなのか」「すぐに病院へ行くべきなのか」と不安になる方も多いでしょう。日常生活で経験する頭痛の多くは命に関わらない一次性頭痛ですが、中には脳卒中やくも膜下出血など重篤な疾患による二次性頭痛もあります。
当院でも「急に激しい頭痛が起きて心配になって来院しました」という方を数多く診察しています。適切な判断基準を知ることで、不要な不安を取り除き、本当に危険な症状を見逃さずに済みます。
この記事では、内科医の視点から急な頭痛への対処法と、緊急受診が必要な危険なサインについて、実例を交えながら詳しく解説します。
頭痛の種類と見分け方
頭痛は大きく分けて一次性頭痛と二次性頭痛の2つに分類されます。まずはこの違いを理解することが、適切な対処への第一歩となります。
一次性頭痛は片頭痛や緊張型頭痛など、頭痛そのものが主な病気である場合を指します。一方、二次性頭痛は脳の病気や感染症など、他の疾患が原因となって起こる頭痛です。
一次性頭痛の特徴
一次性頭痛には主に片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛があります。片頭痛は日本人にとって比較的身近であり、多くの場合は命に関わることはありません。
| 頭痛の種類 | 主な特徴 |
|---|---|
| 片頭痛 | 拍動性、片側性、悪心・嘔吐を伴う |
| 緊張型頭痛 | 締め付けられるような痛み、両側性 |
| 群発頭痛 | 目の奥の激痛、涙・鼻水を伴う |
これらの一次性頭痛は、適切な治療により症状をコントロールできることがあります。ただし、普段とは明らかに違う症状が現れた場合は注意が必要です。
二次性頭痛の危険性
二次性頭痛は命に関わる可能性があるため、早期発見・治療が不可欠です。脳卒中、くも膜下出血、髄膜炎などが代表的な原因疾患となります。
当院でも「今まで経験したことのない激しい頭痛」を訴えて来院され、CT検査やMRI検査が必要と判断し専門医療機関へ紹介するケースがあります。
慢性頭痛との違いを理解する
慢性的に頭痛がある方でも、普段とは性質の異なる急な頭痛が起きた場合は要注意です。慢性化する頭痛との違いを見極めることが重要になります。
- 痛みの強さが普段の何倍も激しい
- 痛みの場所や性質が明らかに異なる
- 随伴症状(発熱や意識障害など)を伴う
これらの変化がある場合は、慢性頭痛をお持ちの方でも医療機関での評価が必要です。
緊急受診が必要な危険な頭痛のサイン
頭痛の中でも特に危険で、一刻も早く病院へ行くべきサインがあります。これらの症状がある場合は、迷わず救急車を呼ぶか、速やかに医療機関を受診してください。
実際の診療現場では、これらのサインを見逃さないことが患者の生命予後を左右することもあります。
突然の激しい頭痛
「バットで殴られたような」「人生最悪の」と表現される突然の激痛は、くも膜下出血の典型的な症状です。
先日、40代の女性が朝起床時から突然の後頭部から首筋にかけての激烈な疼痛を訴えて来院されました。「今まで経験したことのない強烈な痛み」との訴えで、意識レベルも若干低下していたため、すぐに救急搬送を手配し、くも膜下出血と診断されました。
神経症状を伴う頭痛
頭痛と同時に以下のような神経症状が現れた場合は、脳卒中の可能性があります。
| 症状 | 考えられる疾患 |
|---|---|
| 片麻痺(半身の脱力) | 脳梗塞・脳出血 |
| 視覚異常・複視 | 脳梗塞・脳腫瘍 |
| 言語障害・呂律困難 | 脳梗塞 |
| 意識障害 | くも膜下出血・脳炎 |
これらの症状は「FAST」(Face:顔面麻痺、Arms:上肢麻痺、Speech:言語障害、Time:時間)として覚えておくと、緊急時の判断に役立ちます。
発熱を伴う頭痛
高熱と項部硬直(首の硬さ)を伴う頭痛は、髄膜炎症状として緊急性が高い状態です。
特に以下の症状が組み合わさった場合は、細菌性髄膜炎の可能性があり、数時間で生命に関わる状態になることもあります。
- 激しい頭痛と高熱
- 項部硬直(首を前に曲げられない)
- 光過敏(光を眩しく感じる)
- 悪心・嘔吐
急に頭痛が起きた時の受診タイミング
急な頭痛が起きた時、「今すぐ病院に行くべきか」「様子を見ても大丈夫か」の判断は難しいものです。適切な受診タイミングを知ることで、必要な時に迅速な対応ができます。
当院では、患者の皆様からよく「どのタイミングで受診すればよいですか」というご質問をいただきます。
即座に救急受診が必要なケース
以下の症状がある場合は、迷わず救急車を呼ぶか、すぐに救急外来を受診してください。
| 症状 | 判断基準 |
|---|---|
| 突然の激痛 | 今まで経験したことのない強さ |
| 意識障害 | 呼びかけに反応が鈍い・朦朧とする |
| 神経症状 | 麻痺・言語障害・視覚異常 |
| 高熱+項部硬直 | 38度以上の発熱と首の硬さ |
これらの症状は時間の経過とともに悪化する可能性があるため、「様子を見る」のではなく即座の行動が必要です。
翌日までに受診すべきケース
緊急性は高くないものの、早めの医療機関受診が望ましい状況もあります。
- 市販薬で治らない頭痛が3日以上続く
- 頭痛の頻度や強さが徐々に増している
- 軽度の吐き気や食欲不振を伴う
- 頭部外傷後に出現し改善しない頭痛
心配な場合には、夜間でも#7119(救急相談)を利用して専門家の助言を求めることをお勧めします。
自宅で様子を見てもよいケース
以下の条件を満たす場合は、適切な対処法により自宅で様子を見ることも可能です。
- 軽度から中等度の頭痛
- 発熱や神経症状を伴わない
- 市販薬で症状が改善する
- 日常生活に大きな支障がない
ただし、症状の変化に注意を払い、悪化した場合は速やかに受診することが重要です。
急に頭痛が起きた時の自己対処法と市販薬の使い方
軽度から中等度の頭痛に対しては、適切な自己対処法と市販薬の使用により症状を緩和できることがあります。ただし、これらの対処法は一時的な症状緩和を目的とし、根本的な治療ではありません。
診療の際、患者の皆様から「市販薬はどれくらい飲んでも大丈夫ですか」「何時間様子を見れば良いでしょうか」というご質問をよくいただきます。
基本的な対処法
頭痛が起きた時の基本的な対処法は、頭痛の種類によって異なります。まずは以下の方法を試してみましょう。
| 対処法 | 効果的な頭痛の種類 | 実施方法 |
|---|---|---|
| 冷却 | 片頭痛 | 痛む部位を冷たいタオルで冷やす |
| 温熱 | 緊張型頭痛 | 首・肩を温めて血行を改善 |
| 安静 | 全般 | 暗く静かな場所で休息 |
| 水分補給 | 脱水による頭痛 | 常温の水を少量ずつ摂取 |
これらの対処法により30分から1時間で症状が改善することも多くあります。
市販薬による対処法
市販薬は症状に応じて適切に使用すれば、頭痛の緩和に効果的です。ただし、使用方法や期間には注意が必要です。
先日、「毎日市販薬を飲んでいるが頭痛が治らない」という30代男性が来院されました。詳しく話を聞くと、連日の鎮痛薬使用により薬物乱用頭痛を起こしていることが判明しました。
- 用法・用量を必ず守る
- 連続使用は3〜5日以内に留める
- 月に10日以上の使用は避ける
- 他の薬剤との相互作用に注意
病院受診が必要なケース
市販薬を適切に使用しても症状が改善しない場合は、医療機関での評価が必要です。
- 市販薬服用後2時間経っても効果がない
- 薬の効果が徐々に弱くなっている
- 薬を飲む頻度が増えている
- 副作用(胃痛・眠気など)が強い
これらの状況では、処方薬による治療や、頭痛の根本的な原因の検査が必要になることがあります。
検査が必要な頭痛と医療機関での対応
医療機関を受診した際、医師は問診と身体診察により頭痛の原因を評価します。必要に応じてCT検査やMRI検査などの画像検査を行い、二次性頭痛の可能性を除外します。
当院でも、頭痛で来院される方に対して必要に応じて専門医療機関での精密検査をご紹介しています。
問診で重要なポイント
医師は以下の項目について詳しく質問します。これらの情報は、適切な診断と治療方針の決定に不可欠です。
| 問診項目 | 確認内容 | 診断への重要性 |
|---|---|---|
| 発症様式 | 突然発症・徐々に悪化 | 一次性・二次性の鑑別 |
| 痛みの性質 | 拍動性・締め付け・刺すような | 頭痛の種類の特定 |
| 随伴症状 | 悪心・嘔吐・神経症状 | 緊急性の評価 |
| 誘因・増悪因子 | ストレス・体動・光 | 頭痛の分類 |
受診の際は、これらの項目について事前に整理しておくと、診察がスムーズに進みます。
画像検査
すべての頭痛にCT検査やMRI検査が必要というわけではありませんが、以下の場合は画像検査が推奨されます。
- 突然発症の激しい頭痛
- 神経症状を伴う頭痛
- 頭部外傷後の頭痛
- 50歳以降に初発した頭痛
- 頭痛の性質が著明に変化した場合
特に高血圧性脳症が疑われる場合や、脳腫瘍の可能性がある場合は、迅速な画像検査により早期診断・治療につなげることができます。
専門医療機関への紹介基準
当院では、以下の場合に脳神経外科や神経内科などの専門医療機関への紹介を行います。
- 画像検査で異常所見が認められた場合
- 難治性の頭痛で専門的治療が必要な場合
- 薬物治療に反応しない慢性頭痛
- 診断が困難な複雑な症例
適切なタイミングでの専門医紹介により、より精密な診断と効果的な治療を受けることができます。
よくある質問と回答
Q: 頭痛が起きた時、まず何をすればよいですか?
A: まずは症状の重症度を評価してください。突然の激しい頭痛、意識障害、神経症状(麻痺や言語障害)、高熱を伴う場合は迷わず救急受診してください。軽度から中等度の頭痛であれば、安静にして冷却(片頭痛の場合)や温熱(緊張型頭痛の場合)を試し、必要に応じて市販薬を使用します。症状が改善しない場合や悪化する場合は医療機関を受診しましょう。
Q: 市販薬はどれくらい飲んでも大丈夫ですか?
A: 市販の鎮痛薬は用法・用量を守って使用し、連続使用は3日以内に留めることが重要です。月に10日以上使用すると薬物乱用頭痛を引き起こす可能性があります。市販薬を服用しても2時間経っても効果がない場合や、薬を飲む頻度が増えている場合は医療機関での相談をお勧めします。
Q: いつもの頭痛と違う時の判断基準は?
A: 普段の頭痛と比べて痛みの強さが何倍も激しい、痛みの場所や性質が明らかに異なる、発熱や神経症状などの随伴症状を伴う場合は要注意です。特に「今まで経験したことのない頭痛」「人生最悪の頭痛」と感じる場合は、くも膜下出血などの可能性があるため緊急受診が必要です。
Q: 夜間や休日に頭痛が起きた場合はどうすればよいですか?
A: 危険なサイン(突然の激痛、意識障害、神経症状、高熱)がある場合は迷わず救急外来を受診してください。緊急性が判断できない場合は、#7119(救急相談)を利用して専門家の助言を求めることができます。軽度の頭痛であれば適切な対処法で様子を見て、翌日に医療機関を受診することも可能です。
Q: CT検査やMRI検査は必ず必要ですか?
A: すべての頭痛に画像検査が必要というわけではありません。しかし、突然発症の激しい頭痛、神経症状を伴う頭痛、頭部外傷後の頭痛、50歳以降に初発した頭痛、頭痛の性質が著明に変化した場合などでは、二次性頭痛を除外するために画像検査が推奨されます。医師の判断により必要性を評価します。
まとめ
急な頭痛が起きた時は、まず症状の重症度を冷静に評価することが重要です。突然の激しい頭痛、神経症状、意識障害、高熱を伴う場合は生命に関わる可能性があるため、迷わず救急受診してください。
一方で、軽度から中等度の頭痛であれば適切な対処法と市販薬の使用により症状を緩和できることも多くあります。ただし、市販薬で治らない場合や症状が悪化する場合は、医療機関での評価が必要です。
不安な時は一人で判断せず、医療機関や救急相談(#7119)を積極的に活用することをお勧めします。適切な知識と判断基準を持つことで、必要な時に迅速な対応ができ、安心して日常生活を送ることができるでしょう。
急な頭痛でお困りの際は、ステーションクリニック東大宮へお気軽にご相談ください
ステーションクリニック東大宮はJR東大宮駅西口から徒歩0分、ロータリー沿いにある総合クリニックです。
内科・皮膚科・アレルギー科を中心に、高血圧・糖尿病などの生活習慣病から肌トラブルまで、幅広いお悩みに対応しています。
- 完全予約制【ファストパス】で待ち時間を大幅短縮
- 平日夜や土日祝も診療しており、忙しい方でも通いやすい
- 最大89台の無料提携駐車場完備で、お車でも安心して受診できる
- キャッシュレス決済対応(クレジットカード/QRコード決済/交通系IC/電子マネーなど)
「最近、血圧が高めで気になる」「肌のかゆみがなかなか治らない」など、どんな小さなお悩みでもまずはご相談ください。