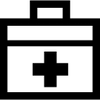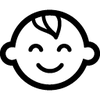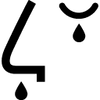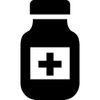肝硬変は進行性の疾患で、初期段階では症状がほとんど現れませんが、病気が進行すると様々な合併症を引き起こします。
実際に当院では、肝硬変の方々から「どのような合併症が起こるのか心配」「症状が現れたときの対処法を知りたい」といったご相談を日々受けています。
本記事では、肝硬変で起こりうる主要な合併症について、それぞれの症状と治療法を実例とともに詳しく解説いたします。
肝硬変とは?原因と病期について
肝硬変は、慢性肝疾患の終末像で、肝細胞が破壊され、線維化が進行した状態です。
日本では推定約30〜50万人の方が肝硬変に罹患しており、年間約14,000人が亡くなる重篤な疾患です。
主な原因疾患
肝硬変の原因は多岐にわたり、それぞれ異なる経過をたどります。
| 原因 | 特徴 |
|---|---|
| B型・C型肝炎ウイルス | 慢性炎症により徐々に進行 |
| アルコール性 | 長期間の過度な飲酒により発症 |
| NASH(非アルコール性脂肪性肝炎) | 肥満や糖尿病に関連 |
| 自己免疫性肝疾患 | 原発性胆汁性胆管炎など |
| その他 | 薬剤性、遺伝性など |
代償期と非代償期の違い
肝硬変は病期により代償期と非代償期に分類され、合併症のリスクが大きく異なります。
代償期では肝機能がある程度保たれているため症状はほとんど現れませんが、非代償期に移行すると様々な合併症が出現します。
- 代償期:肝機能が代償されており、症状は軽微または無症状
- 非代償期:肝機能低下により腹水、黄疸、肝性脳症などが出現
- Child-Pugh分類:A(軽度)からC(重度)まで重症度を評価
門脈圧亢進による主要な合併症
肝硬変の多くの合併症は門脈圧亢進症によって引き起こされます。
門脈は消化管から肝臓への血流を運ぶ重要な血管ですが、肝硬変により肝内の血流抵抗が増加し、門脈圧が上昇します。
食道静脈瘤・胃静脈瘤
食道静脈瘤破裂は肝硬変の最も危険な合併症の一つで、死亡率は10〜20%に達します。
私が過去に勤務していた病院でも、急激な吐血で救急搬送された60歳男性のケースがありました。アルコール性肝硬変の方で、定期検査を受けていなかったため静脈瘤の存在に気づかず、突然の破裂となりました。
| 症状 | 対処法 |
|---|---|
| コーヒー残渣様嘔吐 | 内視鏡的止血術 |
| 大量吐血・下血 | 緊急内視鏡治療 |
| 血圧低下・意識障害 | 輸血・集学的治療 |
腹水と浮腫
腹水は肝硬変の代表的な症状で、門脈圧亢進と低アルブミン血症により生じます。
当院に受診されている50代女性の例では、B型肝炎から肝硬変に進行し、最初は足のむくみから始まり、徐々に腹部膨満感が現れました。利尿薬治療により症状は改善していますが、定期的な経過観察が必要な状態です。
- 初期症状:下肢浮腫、体重増加
- 進行時:腹部膨満感、呼吸困難
- 治療:利尿薬(スピロノラクトン、フロセミド)、塩分・水分制限
- 重症例:腹腔穿刺による除水
肝機能低下による代謝性合併症
肝臓の代謝機能低下により、様々な全身症状が現れます。
これらの症状は日常生活に大きな影響を与えるため、適切な管理が重要です。
肝性脳症
肝性脳症は意識障害を伴う重篤な合併症で、早期の治療介入が必要です。
家族から「最近言動がおかしい」と相談された70代男性を診察したことがあります。軽度の見当識障害から始まり、適切な治療により改善しましたが、早期発見の重要性を痛感したケースでした。
| 病期 | 主な症状 | 治療方針 |
|---|---|---|
| 軽度(I度) | 軽微な意識障害、見当識障害 | ラクツロース内服、リファキシミン内服 |
| 中等度(II度) | 時間・場所の見当識障害 | ラクツロース増量、分岐鎖アミノ酸 |
| 重度(III-IV度) | 昏睡、反応低下 | 入院管理、集学的治療 |
黄疸と胆汁うっ滞
肝細胞の破壊により、ビリルビンの処理能力が低下し黄疸が出現します。
皮膚や眼球結膜の黄染は肝機能低下の重要な指標であり、進行度の評価に用いられます。
- 軽度:眼球結膜の軽微な黄染
- 中等度:皮膚の明らかな黄染
- 重度:全身の強い黄染、かゆみ
- 治療:原疾患の治療、対症療法
その他の代謝異常
肝硬変では筋けいれん(こむら返り)が高頻度で見られ、生活の質を著しく低下させます。
電解質異常や栄養状態の悪化により、様々な症状が現れます。
| 症状 | 原因 | 対処法 |
|---|---|---|
| こむら返り | 電解質異常、循環不全 | 電解質補正、漢方(芍薬甘草湯) |
| 出血傾向 | 凝固因子低下、血小板減少 | 止血剤、血小板輸血 |
| 貧血 | 慢性消化管出血、葉酸欠乏 | 鉄剤、葉酸投与 |
感染症と悪性疾患のリスク
肝硬変の方々は免疫機能の低下により感染症のリスクが高く、また肝がんの発症リスクも著明に増加します。
これらの合併症は生命予後に直結するため、定期的な検査による早期発見が極めて重要です。
特発性細菌性腹膜炎
特発性細菌性腹膜炎は腹水貯留例で起こる重篤な感染症で、迅速な抗生物質治療が必要です。診断の遅れは致命的となる可能性がありますので、特に注意が必要です。
- 主症状:発熱、腹痛、腹水の混濁
- 診断:腹水穿刺による細胞数・細菌検査
- 治療:広域抗生物質の即座投与、アルブミン投与
- 予後:早期治療で予後良好、遅延で重篤化
肝がん(肝細胞癌)
肝硬変から肝がんへの進展リスクは年間約1〜8%と非常に高く、定期的な検査が不可欠です。
| 検査項目 | 目的 |
|---|---|
| 腹部超音波検査 | 小肝がんの早期発見 |
| 血液検査(AFP・PIVKA-II) | 腫瘍マーカー監視 |
| CT・MRI | 詳細な画像評価 |
その他の合併症
肝硬変では多臓器にわたる様々な合併症が出現する可能性があります。
肝腎症候群や肝肺症候群など、重篤な合併症の早期発見には定期的な全身評価が必要です。
- 肝腎症候群:腎機能急激悪化、予後不良
- 肝肺症候群:呼吸困難、酸素化能低下
- 門脈肺高血圧症:右心不全、運動時息切れ
- 皮膚症状:クモ状血管腫、手掌紅斑、女性化乳房
合併症別の治療法と日常管理
肝硬変の合併症治療は、病期や重症度に応じた個別化アプローチが重要です。
当院では、各方の状態に合わせた治療計画を立て、生活の質の維持を最優先に考えた管理を行っています。
薬物療法の基本
肝硬変の薬物療法では、肝機能に応じた用量調整と副作用監視が極めて重要です。
私たちが処方する際は、必ず肝機能検査値を確認し、定期的な副作用チェックを実施しています。
| 合併症 | 主な治療薬 | 注意点 |
|---|---|---|
| 腹水・浮腫 | スピロノラクトン、フロセミド | 電解質異常に注意 |
| 肝性脳症 | ラクツロース、リファキシミン、分岐鎖アミノ酸 | 下痢に注意、定期評価 |
| 静脈瘤予防 | βブロッカー(プロプラノロール) | 血圧・心拍数監視 |
内視鏡治療と外科的介入
食道静脈瘤などの重篤な合併症に対しては、内視鏡治療や外科的治療が必要となります。
- 内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL):出血リスクの高い静脈瘤
- 内視鏡的硬化療法(EIS):細かい静脈瘤の治療
- バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術(B-RTO):胃静脈瘤
- 経頸静脈的肝内門脈大循環シャント術(TIPS):門脈圧減圧
日常生活での管理ポイント
日常生活の管理は合併症予防の要であり、適切な指導により生活の質を大幅に改善できます。
当院では、食事・運動・服薬管理について、なるべく実践的なアドバイスを提供しています。
| 管理項目 | 具体的方法 | 目標値 |
|---|---|---|
| 塩分制限 | 1日6g未満、出汁活用 | 浮腫・腹水軽減 |
| 蛋白質摂取 | 1.0-1.2g/kg/日 | 栄養状態維持 |
| 体重管理 | 毎日同時刻測定 | 週2kg以上増加で受診 |
よくある質問と回答
当院に寄せられる肝硬変の合併症に関する代表的なご質問にお答えします。
皆様の不安や疑問の解決にお役立てください。
Q1. 腹水が溜まったら必ず入院が必要ですか?
軽度の腹水であれば外来での治療が可能です。利尿薬の調整や食事療法により、多くの方は日常生活を継続できます。
ただし、呼吸困難や食事摂取困難を伴う大量腹水の場合は、入院による腹腔穿刺が必要となることがあります。定期的な外来フォローにより、重篤化を予防することが重要です。
Q2. 食道静脈瘤があると言われましたが、日常生活で注意することは?
食道静脈瘤がある場合、破裂予防のための生活習慣の見直しが重要です。
硬い食べ物や刺激物は避け、ゆっくりと咀嚼して食事を摂ってください。急激な腹圧上昇を避けるため、重いものを持ち上げる作業や強い咳は控えましょう。また、定期的に静脈瘤の状態を観察し、必要に応じて予防的治療も検討します。
Q3. 肝硬変でも仕事を続けることはできますか?
代償期の肝硬変であれば、適切な管理のもとで仕事を継続できる方が多くいらっしゃいます。
重要なのは、定期的な受診と服薬遵守、適度な休息の確保です。非代償期に進行した場合は、体調に合わせて勤務形態を調整する必要がありますが、完全に仕事を諦める必要はありません。社会復帰支援も含めた総合的なケアが重要となります。
Q4. 家族にうつる可能性はありますか?
肝硬変自体は感染しませんが、原因となったウイルス性肝炎(B型・C型)は感染の可能性があります。
B型肝炎は血液や体液を介して感染するため、家族内での予防策が重要です。C型肝炎の家族内感染は稀ですが、完全に否定はできません。家族の方のスクリーニング検査や、B型肝炎ワクチン接種について相談されることをお勧めします。
Q5. 定期検査はどのくらいの頻度で受ければよいですか?
肝硬変の定期検査は、病期と合併症の有無により頻度が異なります。
代償期では3〜6か月ごと、非代償期では1〜3か月ごとの受診が推奨されます。血液検査は病状により数か月ごとに行います。症状の変化があれば、予定外でも早めに受診してください。
まとめ
肝硬変の合併症は多岐にわたり、門脈圧亢進による食道静脈瘤や腹水、肝機能低下による肝性脳症や黄疸など、重篤な症状を呈する可能性があります。
特に食道静脈瘤破裂は死亡率10〜20%の危険な合併症であり、定期的な内視鏡検査と適切な予防治療が不可欠です。また、肝がんの発症リスクが年間約1〜8%と高いため、継続的な検査による早期発見が重要となります。
適切な薬物療法と生活習慣の改善により、多くの合併症は管理可能であり、生活の質を維持しながら治療を継続することができます。症状の変化を見逃さず、定期的な医療機関での経過観察を受けることで、重篤な合併症の予防と早期治療が可能となるのです。
東大宮駅徒歩0分・平日夜まで診療のステーションクリニック東大宮へお気軽にご相談ください
肝機能について心配がある方、定期的な経過観察をお考えの方は、ぜひ当院にご相談ください。
ステーションクリニック東大宮はJR東大宮駅西口から徒歩0分、ロータリー沿いにある総合クリニックです。
内科・皮膚科・アレルギー科を中心に、高血圧・糖尿病などの生活習慣病から肌トラブルまで、幅広いお悩みに対応しています。
- 完全予約制【ファストパス】で待ち時間を大幅短縮
- 平日夜や土日祝も診療しており、忙しい方でも通いやすい
- 最大89台の無料提携駐車場完備で、お車でも安心して受診できる
- キャッシュレス決済対応(クレジットカード/QRコード決済/交通系IC/電子マネーなど)
「最近、血圧が高めで気になる」「肌のかゆみがなかなか治らない」など、どんな小さなお悩みでもまずはご相談ください。