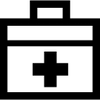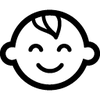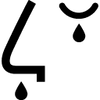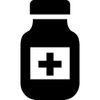長時間の移動や座り仕事を続けていると、突然足に痛みや腫れが現れることがあります。これは「エコノミークラス症候群」と呼ばれる症状で、近年では飛行機での移動だけでなく、新幹線での出張、災害時の避難所生活、さらにはテレワークによる長時間のデスクワークでも発症するケースが報告されています。
当院でも、長距離移動後に足の違和感を訴えて来院される方などで発覚する場合がありますが、重篤な症状に発展する前に早期発見できた事例も少なくありません。エコノミークラス症候群は、適切な知識と対策があれば十分に予防可能な疾患です。
本記事では、エコノミークラス症候群の詳しい原因から具体的な予防法まで、医師としての現場経験を交えながら分かりやすく解説します。皆様の健康維持にお役立ていただければ幸いです。
エコノミークラス症候群とは?
エコノミークラス症候群は、正式には「静脈血栓塞栓症」と呼ばれる病気です。長時間同じ姿勢を続けることで血流が滞り、主に足の静脈に血栓(血の塊)ができる疾患を指します。
この症状が「エコノミークラス症候群」と呼ばれるようになったのは、飛行機のエコノミークラスのような狭い空間で長時間座り続けることで発症しやすいためです。しかし実際には、移動手段や場所を問わず発症する可能性があります。
発症のメカニズム
エコノミークラス症候群の発症メカニズムは、主に2つの段階に分かれます。まず、足の深い静脈に血栓が形成される「深部静脈血栓症(DVT)」が起こります。次に、この血栓が血流に乗って肺の血管に詰まる「肺塞栓症(PE)」へと進行する場合があります。
当院では、長距離移動後に「足がだるい」「少し腫れている気がする」と相談に来られる方々に対し、必要に応じて血液検査などを実施しています。早期の段階であれば、適切な治療により重篤な合併症を防ぐことができます。
無症状のケースが多い
西日本豪雨の被災地で行われた医師チームによる検診では、避難所で生活する住民の多くが無自覚のままエコノミークラス症候群を発症していたことが判明しました。この調査結果は、症状を感じていなくても体内で血栓が形成されている可能性を示しています。
私たちが日常の診療で注意深く観察していると、明らかな症状を訴えない方々でも、詳しく問診を行うと「最近疲れやすい」「階段で息切れしやすくなった」といった軽微な変化を感じている場合があります。
エコノミークラス症候群の主な原因
エコノミークラス症候群の発症には、複数の要因が複雑に絡み合っています。単純に「長時間座っているだけ」が原因ではなく、血流の停滞、血液の性状変化、血管の損傷という3つの要素が組み合わさることで発症リスクが高まります。
ここからは、特に注意が必要な原因について詳しく解説していきます。「なぜ自分が発症したのか」というよくある疑問にお答えできるよう、具体的な発症メカニズムを紹介します。
長時間の同一姿勢による血流停滞
最も代表的な原因が、長時間同じ姿勢を続けることによる血流の停滞です。座った状態では、膝の裏側や太ももの静脈が圧迫され、血液が心臓に戻りにくくなります。
特にふくらはぎの筋肉は「第二の心臓」と呼ばれ、収縮することで血液を心臓に押し戻すポンプの役割を果たしています。しかし、長時間動かないでいると、このポンプ機能が働かず、血液が下肢に停滞してしまいます。
脱水による血液濃縮
長時間の移動中や災害時の避難所生活では、トイレを気にして水分摂取を控える方が多くいらっしゃいます。脱水状態になると血液が濃くなり、血栓ができやすい状態になってしまいます。
私たちがよくお伝えしているのは、「のどが渇いた」と感じる前の段階での水分補給の重要性です。特に高齢の方々は、のどの渇きを感じにくくなるため、意識的な水分摂取が必要になります。
見逃しやすい日常生活でのリスク
エコノミークラス症候群は飛行機での移動時だけでなく、私たちの日常生活の様々な場面で発症するリスクがあります。特に近年では、働き方の変化や生活様式の変化により、新たなリスクシーンが注目されています。
当院では、これらの見逃しやすいリスクシーンで発症した方々の診療を通じて、予防の重要性を実感しています。ここでは、特に注意が必要な日常の場面について具体的に解説します。
| 生活シーン | 主なリスク要因 | 対策 |
|---|---|---|
| テレワーク | 長時間座位、運動不足 | 1時間ごとの立ち上がり |
| 避難所生活 | 狭いスペース、ストレス、脱水 | 定期的な足の運動、水分確保 |
| 高齢者の日常 | 活動量減少、筋力低下 | 軽い運動習慣、水分意識 |
テレワークや長時間のデスクワーク
在宅勤務の普及により、1日8時間以上座り続ける方が急増しています。オフィスにいた頃は会議室への移動や同僚との会話で自然に立ち上がる機会がありましたが、自宅では意識的に動かない限り、同じ姿勢を続けがちです。
私たちが診療で確認すると、テレワーク開始後に足のむくみや疲労感を訴える方が明らかに増加していることが分かります。特に締め切りが迫った仕事や集中を要する作業では、気がつくと数時間動いていないということも珍しくありません。
災害時避難所での生活
西日本豪雨の際の小学校避難所では、住民検診で多くの方が無自覚のまま足に血栓を抱えていることが確認されました。避難所では限られたスペースで過ごすため、思うように体を動かせない状況が続きます。
さらに、ストレスや不安から食欲不振になったり、給水の制限から水分摂取を控えたりすることで、血栓形成のリスクがより高まってしまいます。
高齢者の日常生活
高齢になると活動量が自然に減少し、テレビを見る時間や座って過ごす時間が長くなります。当院では、定期的に通院される高齢の方々に対し、日常の活動状況について詳しくお聞きしています。
- 長時間のテレビ視聴(3時間以上連続)
- 読書や手芸など座位での趣味活動
- 外出頻度の減少による運動不足
- 水分摂取量の自然な減少
これらの要因が重なることで、日常生活の中でもエコノミークラス症候群を発症するリスクが高まります。
効果的な予防法
エコノミークラス症候群の予防には、血流の改善、適切な水分補給、そして生活習慣の見直しが重要です。ここでは、すぐに実践できる具体的な予防法から、長期的な健康管理まで、包括的な対策をご紹介します。
当院では、リスクの高い方々に対して個別に指導を行っており、実際に予防効果を実感されている事例も多数あります。医学的根拠に基づいた効果的な方法を中心に解説していきます。
血流改善のための運動と姿勢
最も重要なのは、定期的な下肢の運動による血流促進です。座ったままでもできる簡単な運動を1〜2時間おきに行うことで、血栓形成のリスクを大幅に減らすことができます。
一般的に推奨される運動は、皆様が続けやすく効果的なものです。特にふくらはぎの筋肉を意識的に動かすことで、血液を心臓に押し戻すポンプ機能を活性化できます。
- 足首の回転運動(時計回り・反時計回り各10回)
- つま先の上下運動(かかとを床につけたまま20回)
- 膝の屈伸運動(座ったまま片足ずつ10回)
- 可能であれば立ち上がって軽い歩行(2〜3分)
適切な水分補給の方法
水分補給では、単に水を飲めばよいというわけではありません。血液の粘度を下げ、血流を改善するためには、適切なタイミングと量での摂取が重要です。
当院では、カフェインやアルコールは利尿作用があるため、長時間の移動時や座位での作業時には控えることをお勧めしています。また、トイレを気にして水分を控える方が多いのですが、これは体調にとっては一般的に逆効果であることを強調してお話ししています。
衣服と環境の工夫
締め付けの少ない衣服の選択も重要な予防策の一つです。特に腰回りや太もも、ふくらはぎを圧迫する衣服は血流を妨げる原因となります。
| 予防アイテム | 効果 | 使用場面 |
|---|---|---|
| 弾性ストッキング | 段階的圧迫で血流改善 | 長時間移動、手術後 |
| ゆったりした衣服 | 血管圧迫の軽減 | 日常生活全般 |
| クッション | 座位での圧迫分散 | デスクワーク、移動時 |
症状の早期発見のポイント
エコノミークラス症候群の症状は段階的に現れることが多く、初期の軽微な症状を見逃さないことが重要です。重篤な肺塞栓症に進行する前に、適切な治療を受けることで予後を大きく改善できます。
当院での診療経験から、「これくらいの症状で受診しても良いのだろうか」と迷われる方が非常に多いことを実感しています。しかし、早期発見・早期治療が最も重要であり、些細な症状でも気軽にご相談いただきたいと考えています。
見逃してはいけない初期症状
足の症状から始まることが多いエコノミークラス症候群では、以下のような変化に注意が必要です。これらの症状が一つでも当てはまる場合は、早めの受診をお勧めしています。
私たちが診療で最も注意深く確認しているのは、「いつもと違う」と感じる感覚です。医学的な検査値だけでなく、日常生活での些細な変化こそが重要なサインとなる場合があります。
- 片足だけのむくみや腫れ
- ふくらはぎや太ももの痛み・圧痛
- 足の皮膚の色の変化(赤み・青み)
- 足の温感(触ると他の部位より温かい)
- 歩行時の違和感や疲労感の増加
緊急受診が必要な症状
血栓が肺に移動した場合の肺塞栓症では、生命に関わる症状が現れることがあります。これらの症状が現れた場合は、迷わず救急車を呼ぶか、直ちに医療機関を受診してください。
当院では、これらの症状について本人やご家族に詳しく説明し、緊急時の対応についてもお話ししています。特に高リスクの方々には、症状の変化を記録していただくこともあります。
| 症状の分類 | 具体的な症状 |
|---|---|
| 足の症状 | 片側の腫れ・痛み・色調変化 |
| 呼吸器症状 | 息切れ・胸痛・咳 |
| 重篤な症状 | 激しい胸痛・失神・血痰 |
医療機関での診断と治療
エコノミークラス症候群が疑われる場合、必要に応じて血液検査(Dダイマー測定)や画像検査などが行われます。これらの検査により、血栓の有無や位置、重症度を把握します。
※当院ではエコノミークラス症候群の画像検査を実施しておりませんので、必要な場合には近隣の病院などに紹介させていただきます
治療法は症状の程度により異なりますが、軽症例では抗凝固薬による内科的治療が中心となります。重症例では、血栓溶解療法や外科的治療が必要となる場合もあります。
よくある質問と回答
当院に来院される方々から頂く、エコノミークラス症候群に関する質問をまとめました。日常の診療でよく聞かれる疑問について、医師としての経験を基にお答えします。
Q: 何時間座り続けると危険なのでしょうか?
A: 一般的に4時間以上の連続した座位で発症リスクが高まると言われていますが、個人差があります。当院では、少なくとも2時間おきに立ち上がることを推奨しています。特に高齢の方や基礎疾患をお持ちの方は、1時間おきの運動をお勧めしています。重要なのは時間よりも、定期的に下肢を動かすことです。
Q: 妊娠中でも長時間の移動は大丈夫ですか?
A: 妊娠中は血液の凝固能が高まるため、エコノミークラス症候群のリスクが上昇します。当院では、妊娠中の長距離移動の際は、必ず産科医師と相談することをお勧めしています。また、弾性ストッキングの着用や、より頻繁な足の運動が必要です。妊娠後期では、特に注意深い対応が求められます。
Q: どのような水分を、どのくらい摂取すれば良いですか?
A: 基本的には常温の水が最も適しています。コーヒーや緑茶などのカフェイン含有飲料、アルコール類は利尿作用があるため避けることをお勧めします。摂取量の目安は、移動時間1時間につきコップ1杯と言われていますが、心疾患や腎疾患をお持ちの方は主治医と相談の上で調整してください。
Q: 弾性ストッキングは本当に効果がありますか?
A: 医学的に効果が証明されている予防法の一つです。当院では、長時間の移動や手術後の方々に積極的にお勧めしています。段階圧迫により血液の流れを改善し、血栓形成を予防します。ただし、サイズが合わないものは逆効果となる場合があるため、適切なサイズ選択が重要です。
Q: 一度発症したら、再発しやすいのでしょうか?
A: 一度発症された方は、再発リスクが高くなることが知られています。当院では、初回発症後の方々に対して、より厳格な予防指導を行っています。抗凝固薬の継続服用、定期的な検査、生活習慣の改善が重要です。不安を感じたときは、遠慮なくご相談いただければと思います。
まとめ
エコノミークラス症候群は、長時間の同一姿勢による血流停滞、脱水による血液濃縮、個人の体質的要因が複合的に作用して発症する疾患です。飛行機での移動だけでなく、テレワーク、災害時の避難生活、高齢者の日常生活など、様々な場面でリスクが存在することをご理解いただけたでしょうか。
最も重要なことは、定期的な下肢の運動と適切な水分補給による予防です。当院では、1〜2時間おきの足首運動やこまめな水分摂取を推奨しており、実際に多くの方々が予防効果を実感されています。
症状の早期発見も大切なポイントです。片足のむくみや痛み、呼吸困難などの症状が現れた場合は、迷わず医療機関にご相談ください。適切な診断と治療により、重篤な合併症を防ぐことが可能です。皆様の健康な日常生活のため、今日からできる予防対策を実践していただければと思います。
東大宮駅徒歩0分・平日夜まで診療のステーションクリニック東大宮へお気軽にご相談ください
長時間の移動後の足の違和感や、デスクワークによる血流の悪化など、エコノミークラス症候群に関するご不安がございましたら、ステーションクリニック東大宮へご相談ください。
JR東大宮駅西口から徒歩0分、ロータリー沿いにある総合クリニックです。
内科・皮膚科・アレルギー科を中心に、高血圧・糖尿病などの生活習慣病から肌トラブルまで、幅広いお悩みに対応しています。
- 完全予約制【ファストパス】で待ち時間を大幅短縮
- 平日夜や土日祝も診療しており、忙しい方でも通いやすい
- 最大89台の無料提携駐車場完備で、お車でも安心して受診できる
- キャッシュレス決済対応(クレジットカード/QRコード決済/交通系IC/電子マネーなど)
「最近、血圧が高めで気になる」「肌のかゆみがなかなか治らない」など、どんな小さなお悩みでもまずはご相談ください。